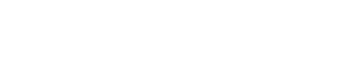認定特定非営利活動法人アサザ基金
認定特定非営利活動法人アサザ基金は、茨城県霞ヶ浦,北浦流域を活動の中心として、耕作地の放棄や人口流出によって急速に失われつつある里山などの再生活動や保全を行い、生物多様性の維持再興と地域社会の活性化を目的とし、活動によって地域社会の環境整備と人的交流の場を再構築することで、循環型地域のモデルとなることを目指しています。今回は代表理事の飯島さんにお話を伺いました。

総合学習で学校の近くの谷津田の再生に取り組む子ども達
現在お取り組みの分野に興味を持ったきっかけを教えてください。
都内で過ごした中学生時代に環境問題に興味を持ったことが始まりでした。当時は水俣病などの公害が広がりを見せている時代で、光化学スモッグが原因で課外授業が中止になる事もありました。
当時は佐渡にいたトキが8羽しかいなくなってしまい、このまま放置したら絶滅は間違いないと頻繁に報道されていました。トキは元々里山や水田など日本中に生息しており、とても身近にいた生き物だったにも関わらず、人間の生き方が変わってしまったために絶滅に追い込まれつつあることを知り、とてもショックを受けました。そして、人間のせいで周りの生き物たちや環境に負荷をかけ、多くの生き物を絶滅させていくというあり方をなんとか変えていきたい、と漠然と思い始めたのです。
また、同時期に僕にとって大きな影響を与えたのが水俣病の存在でした。胎児性水俣病という、生まれながらに大きな障害を負った方が僕と同じ年だということを知り、身近な問題と感じたのです。水俣の問題では不知火海の豊かな海の中で自然と調和し、暮らしを立てていた地元の人たちが一番の犠牲者となっていました。公害の原因となった都会の人ではなく、自然の中で調和して生きている人ほど文明の負債みたいなものを負わされていく。そういう考えが中学生の頃僕の中で非常に大きな問いとして芽生えたのです。それ以来独学で環境のことや生物学を学ぶようになりました。
飯島さんにとっての環境問題に携わる原動力はなんでしょうか。
自分の子どもの頃は都内近郊でも里山がいっぱい残っていて、毎日のように野山で遊んでいました。特に記憶にあるのが、当時は雑木林で落ち葉を集めたり、榾木で椎茸を栽培したり、自然が人の暮らしの場所であると共に生き物がたくさん共存する場所だったという事です。それらが原体験、原風景として僕の中に残っていて、今の子ども達にもそういう原体験をさせたいと思い、たくさんの子ども達が里山に来るような取り組みを続けています。また、普段から総合学習として全国の学校を廻って授業をやっていますが、子ども達から本当に素晴らしい視点や意見が湧き上がってきて、それが糧になっています。特にテーマを決めずに子ども達の中からテーマを引き出して、子ども達自身の中から湧いてきた問いを深めてもらう過程で、思わぬ方向の面白い発想で、思いもつかないような深い言葉が出てくることがある。これが僕の原動力として、この活動を続けてこれた大きな要因となっています。

谷津田で生き物探しに夢中な子ども達(めだかやどじょう、やご等)
これまで活動を続けてきた中で最も印象的な出来事を教えてください。
1995年からアサザ・プロジェクトに着手したのですが、環境問題への取り組みを限られた分野の中だけで収束させるのではなく、農業や工業、教育や公共事業など、あらゆる分野と繋がりを作って、社会全体を大きく変えていけるような仕組みを作りたいと考えていました。
当時の建設省には湖の中で市民も参加する公共事業の提案を持って行きました。この公共事業では当時コンクリートで舗装されてしまっていた霞ケ浦を自然に戻すことを主眼とし、周辺環境の整備も併せて行いました。周辺環境の整備では、湖の環境が良くなれば魚も獲れるようになると漁業協同組合を誘い、上流の森の間伐材も使ったら林業の人たちも助かるだろうからと森林組合にも話を持ちかけ、そして農業関係の人にも生協にも参加してもらって、学校の教育の一環としても関わってもらってと、たくさんの人と一緒に水辺の環境を良くしていくという取り組みを始めたところ、95年から2000年までの間に1万人以上の人たちが参加してくれました。とても画期的な出来事となりました。
しかしながら、この事業が短期間でうまくいき過ぎてしまったが為に、関係者内部で大きな反発が生じてしまい、単発の特異事例としてその取り組みが終わってしまったのです。今振り返ってみると、当時はもっと他のアプローチがあっただろうと思うことがありますが、学びの多い体験でした。
FITからの寄付金の使い道について教えてください。
寄付金は里山体験の取り組みにも使われてはいますが、主には機械の導入に充てています。サポーター企業の協力を得ながら放棄田をもう一度整備し、米作りを行っていますが、この谷津田は一部のエリアに過ぎず、他にも広い範囲で水源地の再生を進めています。そのため、限られたマンパワーではやはり機械に頼らざるを得ないのが実情です。とはいえ、谷津田は昔ながらの田んぼで水が湧いていて泥深い場所なので、通常の大型機械を導入することもできない。こうした条件の悪い場所で使用できる機械をFITの寄付金を利用して購入しました。また、除草剤を使わないので、草刈りも大変な労力が必要となります。さらには、水源地の周りの放置竹林は放っておくと竹が水を全部吸い上げてしまって、水が田んぼに行き渡らなくなってしまいます。そうした放置竹林を減らす取り組みも行っているのですが、その竹もチップにして田んぼの栽培に有効に使えないかと模索しています。これらの取り組みに利用する機械も今回購入しました。

泥深い田んぼで活躍するカゴ車輪付き耕運機
この記事を見てくれている方々へのメッセージをお願いします。
FITにはたくさんの方々が関わっていますが、異なる分野の社会的な課題に取り組んでらっしゃる方々とぜひ繋がっていきたいです。例えば、こども食堂の子どもたちやそこに関わる人たちに谷津田に来てもらって、田植えと稲刈りだけでもいいのでお米を作ってもらう。そうすることでみなさんが自分たちで使う無農薬のお米が確保できるし、子どもたちも里山の体験ができる。
様々な社会課題に取り組んでいるみなさんと、私たちが作り上げてきた場を繋げて、そこにまた何かを繋げて、そんなアイデアをぜひ一緒に作っていきたいです。
認定特定非営利活動法人アサザ基金
http://www.asaza.jp