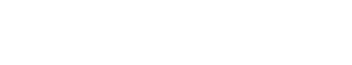NPO法人となりのかいご
NPO法人となりのかいごは、介護を理由に家族の関係が崩れてしまわないことを目指し、企業へ出張しての介護セミナー、個別介護相談、情報発信を行い、誰もが最期まで家族と自然に過ごせる社会の実現に取り組んでいます。今回は、代表理事である川内さんにお話を伺いました。。
 企業向け介護セミナーの様子
企業向け介護セミナーの様子
ご自身の経歴と何がきっかけで団体を始めようと思われたか教えてください。
訪問介護員や認知症専門のデイサービス施設の職員等、介護職に従事していた時、一生懸命家族の介護をされている方が追い込まれていく等、介護の現場でのトラブルを垣間見てショックを受けたり、自分も同じ状況に置かれたらと課題を認識し、介護の難しさを感じたりする面が多々ありました。実は、私の父母も介護・福祉の仕事をしていましたが、私自身は外資系のコンサルティング企業に勤務した際に、事業再生に関わり解雇など厳しい対応をしなければならない業務も経験したことから、やはり人を直接支援する仕事をしたいと思い選んだ道が介護職でした。しかし、そうした介護の現状を目の当たりにして、当事者が「助けてほしい」とSOSを送る、苦難に直面する時点よりももっと手前の段階で手を差し伸べられることがあるのではないかと考え、2008年に市民団体として「となりのかいご」の活動を開始し、2014年にはNPO法人を立ち上げました。
これまでNPOの活動を続けてきて最も困難だった、あるいは良かったと思うことは何ですか?
活動を始めて、介護分野における閉塞感を何とか変えていきたいと思ったものの、どこにフォーカスを当てて、具体的に何をしたいのか悩ましく感じていた時期がありました。大学でも福祉・介護の勉強をしていましたが、家族による要介護者の虐待はあまりにも手に負えないような深遠な問題でアンタッチャブルな分野と捉えられ、私自身も虐待防止といったことへの関わりには怖れがありました。しかし、ここから逃げていては始まらないし、目を背けながら介護の業界にい続けることはできないと強く感じるようになりました。明白な問題として存在するのに、見て見ぬふりをしながら、具体的な虐待行為を発見した時にだけ通報するといったことでは納得がいきませんでした。その結果、「早期の支援」を導入すれば効果が得られるのではないか、という仮説を立てました。そして、色々な出会いがあって、虐待防止活動として企業での支援というところにたどり着き、その方向性を求めていくうちに、事業運営をきちんとできるようになっていきました。高齢者の虐待防止をテーマにしていることで私のやりたいことはそれしかないと活動理念が一致し、納得感を持って仕事ができていると今は感じています。
 祖母のヒデ子さんと川内代表
祖母のヒデ子さんと川内代表
FITからの寄付金はどのように使用されていますか?
改正育児介護休業法が2025年4月から段階的に施行されることで、企業の義務が新たに発生しますが、仕事と介護の両立のリテラシーにつながる、人事部門を中心にした企業の検討や体制整備がまだ十分でない状況が見られました。そのような状況を視野に入れて、改正法への各企業の対応方法に関する解説動画の作成と広報活動に取り組みました。FITの寄付金をもとに、「従業者が仕事と介護を両立できるよう」前向きに検討する日本全国の企業を対象にした動画展開の取り組みをタイムリーに実施することができました。
私たちからはどのような支援ができるでしょうか?
皆さんと共に、これからも介護に関して正しい認識を広げていきたいと思います。今年は法改正をきっかけにして解説動画を制作しました。動画等の手段を通して、理解促進を図り、介護に直面する前から家族と対話し、適切な距離感をとれるような社会を実現していきたいと思います。まずは、私たち一人ひとりが自分ごと化をすることから始められればと感じます。
今後はどのような活動の広がりを考えていますか?
となりのかいごでは、企業内介護セミナーの実施、企業内での仕事と介護の両立に関する個別相談に加えて、家族介護に関する書籍やラジオ等での情報発信を行っています。見つけた課題を日々解決しながら事業を行える現状を大切にしながら、これからも、これまでと同様な支援先に対して、NPO法人としてより本質的な支援を届けたいと思っています。また、近年は、政策への提言の機会もいただいたりするようになりました。例えば、厚労省の研究会が仕事と介護の両立支援に関するガイドラインを策定する上で、意見を提供するといった活動です。こうした活動を通して「高齢者・介護を支援する分野」でのプレイヤーを増やしていく応援をする役割も担っていきたいと思います。
 企業への出張介護相談の様子
企業への出張介護相談の様子
最後にこの記事を読んでいる方にメッセージをお願いします。
家族の介護というのは、家族ときちんと向き合い、適切な距離感で接することで、介護者にとって必ずしも大変で、辛い、難しい課題なだけではなく、「その人が望む生き方ができるよう教えてくれる出来事」「人生の糧」を得られる経験にもなると思います。「自分の親がどうしたらその人らしく生きられるようになるのだろう」と考えたり、家族の介護をする介護者にとっても「自分はどのように生きていきたいのか?」自分の持っている価値観を見直し、あらためて考える機会にもなります。一般に、育児に比べて、介護の方が個別のケースの多様性が非常に顕著だと考えられています。親の介護は自分がやらなくてはといった固定観念も日本では根強いかもしれません。NPO法人となりのかいごでは、一年間に700件以上の個別相談等の取り組みを行っていますが、シンプルにこちらが良い介護、あちらは悪い介護といった区別があるわけではありません。私は、家族だからこそ距離感の取り方が難しいとわかりつつも、親子の関係が良好であることがおそらく唯一の介護の汎用的な評価軸なのではないかと思っています。介護の苦悩自体が話題になりがちですが、介護を理由に家族の関係が崩れてしまうことなく、誰もが最期までその人らしく自然に過ごせる社会の実現を目指してアウトリーチ活動に取り組んで参りますのでこれからも皆さんのご支援をお願いいたします。
 [上段中央] 川内代表理事 [その他左上から]FIT2025実行委員の小林、濱田、大西、山本、永井
[上段中央] 川内代表理事 [その他左上から]FIT2025実行委員の小林、濱田、大西、山本、永井
NPO法人となりのかいご
https://www.tonarino-kaigo.org/
【経営者・人事部の方向け動画】 法改正と企業の義務を解説
https://youtu.be/oAqUM3wYmyg
【従業員向け研修動画①】支援制度の活用方法と注意点
https://youtu.be/7NuUhMFE7pI
【従業員向け研修動画②】介護の基礎知識と準備を解説
https://youtu.be/9mpocmqz2mg
【従業員向け研修動画③】介護体験者インタビュー | ゲスト 柴田理恵 氏
https://youtu.be/3H3yCKT9trk